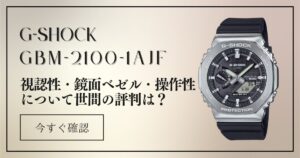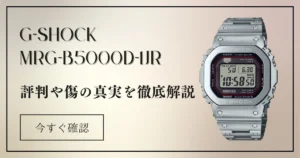こんにちは、CHRONOBLE運営者のNAOYAです。
高級腕時計、特にグランドセイコーやカシオ MR-Gのスペックを見ていると、必ずと言っていいほど目にする「ザラツ研磨」という言葉。
皆さんも気になっていませんか?
私も最初は「時計をピカピカに光らせる特別な磨き方かな?」くらいに思っていました。
でも、ザラツ研磨について調べてみると、ネット上では「意味ない」とか「ひどい」なんていう、ちょっとネガティブな言葉が関連して出てくることもあって、「え、どういうこと?」と混乱したんです。
一般的な「バフ研磨との違い」もイマイチ分かりにくいですし、中には「自分で」DIY研磨できないかな?なんて考える人もいるかもしれません。
ですが、さらに深く調べてみたところ、これらの多くは「誤解」から生まれていることが分かりました。ザラツ研磨の本当のすごさは、単にピカピカにすることではなかったんです。
この記事では、「ザラツ研磨」の本当の役割、なぜ「プラチナ」素材だと研磨が格段に難しくなるのか、そしてなぜグランドセイコーやカシオがこの技術にこだわり続けるのか。
私が調べて納得した「歪みなき鏡面の美学」について、分かりやすくまとめてみました。この技術の奥深さを知ると、時計を見る目が変わるかもしれませんよ。
- ザラツ研磨の本当の意味と「下地処理」という役割
- 一般的なバフ研磨との決定的な違い
- グランドセイコーとカシオ MR-Gにおける哲学の違い
- 素材(プラチナなど)による研磨難易度と職人技
- ザラツ研磨の本当の意味と下地処理という役割
- 一般的なバフ研磨との決定的な違い
- グランドセイコーとカシオ MR-Gにおける哲学の違い
- 素材(プラチナ等)による研磨難易度と職人技
ザラツ研磨とは?技術の核心

まずは「ザラツ研磨」の基本からですね。この技術が「何を目的」としていて、「なぜ特別」なのか、その核心に迫ってみたいと思います。
私たちが「ピカピカ」という言葉でイメージするものとは、ちょっと違うかもしれません。
ザラツ研磨の核心的な定義

ザラツ研磨とは、一言でいうと「歪みのない鏡面を生み出すための、極めて高度な研磨技術」のこと。
時計のケース側面なんかに光が当たった時、景色や光の線がフニャッと歪まず、まるで平らな鏡のように「真っ直ぐ」に反射する状態。あれこそがザラツ研磨の真骨頂なんです。

この完璧な平面があるからこそ、ケースの面と面が交わる「稜線(りょうせん)」、つまりエッジの部分が、ダレずに鋭く(シャープに)際立ちます。
ピカピカに磨こうとすると角が丸まってしまいがちですが、ザラツ研磨は「完璧な平面」と「鋭いエッジ」という、相反する要素を両立させる技術なんですね。
ザラツ研磨の語源と由来

「ザラツ」って、ちょっと不思議な響きですよね。これは日本語ではなく、もともとはスイスの「ザラツ兄弟社(Sallaz)」という会社の名前に由来しているそうです。
1960年代、セイコーが高級時計の品質を飛躍的に上げるために、このSallaz社製の高性能な平面研磨機を導入しました。
面白いのはここからで、最初は「Sallaz社の機械でやる研磨」という意味だったのが、いつしか日本国内で独自の進化を遂げたんです。
今では、単にその機械を使うことではなく、機械の性能を限界まで引き出す日本の「熟練職人の手作業による技術」そのものを指す言葉に。
 管理人
管理人道具の名前が「技」の代名詞になるって、なんだか日本のものづくりらしいストーリーだなと思います。
バフ研磨との決定的な違い

磨くと聞くと、私たちはバフ研磨をイメージすることが多いかもしれません。高速で回転する柔らかい布(バフ)に研磨剤をつけて、表面を撫でるように磨いて艶を出す、あれです。
でも、ザラツ研磨は根本的に違います。ザラツ研磨は、回転する硬い平面のディスク(定盤)に研磨剤を塗り、そこに職人がケース(部品)を手で押し当てて磨いていきます。

これはもう「撫でる」というより「削る」に近い、アグレッシブな「研削」作業です。硬い平面に押し当てるからこそ、角が丸まらず、シャープなエッジと平面が出せるわけです。
この違いは、目的の違いに直結しています。
| 比較項目 | ザラツ研磨 | 一般的なバフ研磨 |
|---|---|---|
| 主目的 | 「面を出す」(平滑にする・歪みを取る) | 「艶を出す」(光らせる) |
| 動作 | 硬い平面に「押し当てる」(研削) | 柔らかい布で「撫でる」(研磨) |
| 仕上がり | 歪みのない平面、シャープな稜線 | 光沢は出るが、角が丸まりやすい |
下地処理という重要な役割

下地処理での役割が、ザラツ研磨を理解する上で一番大切なポイントであり、「意味ない」「ひどい」といった誤解が生まれる原因かなと思います。
実は、ザラツ研磨は「最終的な鏡面仕上げ」そのものではなく、厳密には「下地処理(下地研磨)」の一工程なんです。
最も多い「誤解」
まずはザラツ研磨の本質をお伝えします。
「ザラツ研磨 = ピカピカの最終仕上げ」ではありません。 「ザラツ研磨 = 完璧な最終仕上げ(鏡面)を実現するための、最も重要な下地づくり」が真実です。
時計の研磨は何段階にも分かれていますが、ザラツ研磨は、最終的な艶出し(バフ研磨)の「前」に行われます。この段階で、いかにケースの面を歪みなく平滑にするか、エッジを立てるかが勝負なんです。
考えてみれば当たり前かもですが、歪んだキャンバス(下地)の上にいくら絵の具(バフ研磨)を塗っても、歪んだ絵(鏡面)しか生まれないですよね。
ザラツ研磨は、完璧な鏡面仕上げを実現するための、最も重要で過酷な「土台づくり」なんです。これが「意味ない」なんてことは、絶対にあり得ないわけです。
機械化できない職人技の領域

「Sallaz社の機械を使うなら、自動化(機械化)できるのでは?」と思うかもしれません。私もそう思っていました。でも、これができないそうなんです。
理由は、グランドセイコーやMR-Gのケースデザインが、自動化が追いつかないほど複雑に進化しているから。
ザラツ研磨は、職人がケースを「素手」で持って、回転するディスクに当てていきます。この時、以下の感覚が求められるそうです。
- 圧力の均一性:歪みのない平面を作るため、指先で均一な圧力をかけ続ける感覚。
- 角度の固定:複雑な形状のケースを、寸分違わぬ角度で固定し続ける技術。
これらは、現在のロボットでは再現が難しい「感覚」の領域なんだとか。デザインが進化するたびに、職人の技も進化し続けているんですね。

ちなみに、「自分でDIY研磨できないか?」という疑問ですが、この事実を知ると非現実的だと分かりますよね。専門の機械と、何年にもわたる修練を積んだ職人の感覚があって初めて成立する技術なので、私たちが手を出せる領域ではなさそうです。
プラチナなど素材と研磨難易度

ザラツ研磨のすごさは、研磨する「素材」によって難易度(=作業時間)が劇的に変わることからも分かります。
グランドセイコーの製造を担うセイコーエプソンの情報によると、ステンレススチールを磨く時間を「1倍」とした場合、素材ごとの研磨時間は以下のようになるそうです。
素材別 研磨時間の目安
- ステンレススチール: 基準(1倍)
- チタン / 18Kゴールド: 1.5倍 の時間
- プラチナ: 5倍から6倍 の時間
プラチナがステンレスの5〜6倍! これは驚異的な数字ですよね。プラチナは非常に粘り気が強い金属で、研磨が極めて難しいそうです。
時計の価格が「素材の地金代」だけで決まっているのではなく、この「研磨工数」というクラフトマンシップの対価が大きく含まれていることが、この数値からよく分かります。
※上記の数値はあくまで一般的な目安であり、モデルのデザインや状態によって変動する可能性があります。
ザラツ研磨が輝く2大ブランド

このスゴイ技術、具体的にはどのブランドがどう使っているんでしょうか。ザラツ研磨を語る上で欠かせない、日本の誇る2大ブランド、グランドセイコーとカシオ G-SHOCK MR-Gのケーススタディを見ていきますね。
同じ技術でも、哲学が違うと使い方が変わるのが面白いところです。
グランドセイコーと輝きの文法

ザラツ研磨と聞いて、真っ先に「グランドセイコー」を思い浮かべる人は多いと思います。まさにその通りで、グランドセイコーにとってザラツ研磨は、ブランドのアイデンティティそのものと言ってもいいかもしれません。
グランドセイコーのデザイン哲学は「セイコースタイル」と呼ばれ、光と影の調和による日本の美意識を表現しています。この哲学を実現するために、ザラツ研磨が必須なんです。
ザラツ研磨が生み出す歪みのない鏡面が光を鋭く正しく反射し、シャープな稜線が明確な影を生み出す。この鮮やかな光と影のコントラストこそが、グランドセイコーの「燦然(さんぜん)たる輝き」の正体なんですね。
グランドセイコーにとってザラツ研磨は、単なる技術ではなく、「輝きを生み出すための文法」そのものなのだと私は解釈しています。
グランドセイコーの哲学や、その魅力については、グランドセイコーは期待を超える腕時計!何故やめとけと噂される?の記事でも詳しく解説していますので、よければご覧ください。
カシオ MR-Gと剛健なる造形美

一方、ザラツ研磨はグランドセイコーの専売特許ではありません。カシオも、G-SHOCKの最上位ライン「MR-G」でこの技術を積極的に採用しています。
MR-Gは、G-SHOCKの絶対的なタフネスと、日本の美意識や高級時計の仕上げを融合させたシリーズです。
カシオがザラツ研磨を採用する目的は、グランドセイコーの輝きとは少し文脈が違います。MR-Gの目的は、主に「シャープな造形美を実現するための下地処理」としてです。
MR-Gのケースやブレスレットは、耐衝撃性を高めるために、たくさんの金属パーツが複雑に組み合わさっています。ザラツ研磨は、これら「パーツの一つひとつ」に施されます。個々のパーツのエッジを際立たせ、平面を出すことで、全てを組み上げた時に、まるで日本の「鎧(よろい)」のような、重厚でシャープな立体感が生まれるんです。
タフネスと美しさを両立させるため、カシオもまたこの手のかかる研磨技術を選んでいるんですね。
MR-Gが「一生もの」となり得るのか、その耐久性や哲学については、GショックMRGは一生ものとなるか?寿命と耐久性や選び方を徹底解説の記事で詳しく触れています。
ブランドによる目的の比較
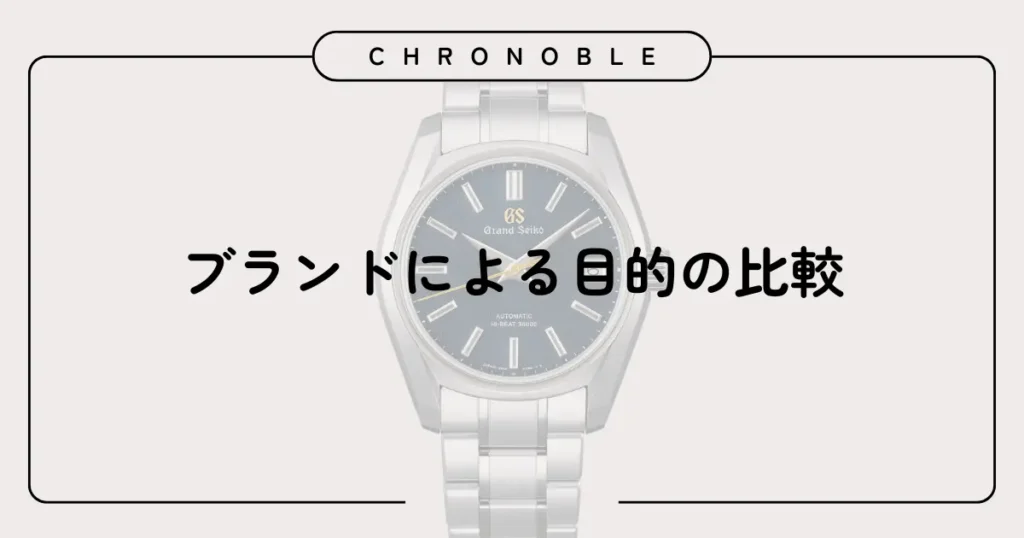
同じザラツ研磨でも、ブランドの哲学によって目的が異なることがよく分かります。この2ブランドを比較してみると、技術の多面性が見えてきて面白いです。
| 比較項目 | グランドセイコー (Grand Seiko) | カシオ G-SHOCK (Casio MR-G) |
|---|---|---|
| 目的・哲学 | 「燦然たる輝き」の実現。 (光と影の調和) | 「シャープな造形美」の実現。 (タフネスと高級感の両立) |
| 技術的役割 | 歪みのない平面と鋭い稜線。 美の根幹。 | 複雑な金属パーツのエッジを際立たせる下地処理。 |
| 技術的特徴 | 1960年代からの伝統。 素材(プラチナ等)による難易度の差が明確。 | 多数のパーツ一つひとつに施される。 DLCなど他処理との組み合わせも多い。 |
グランドセイコーは「光の反射」をコントロールするために、カシオ MR-Gは「複雑な造形」を際立たせるために、それぞれザラツ研磨を用いている、と言えるかなと思います。
グランドセイコーの代表モデル

ザラツ研磨の美しさが特に分かりやすいモデルとして、個人的には「62GS」のデザインを継承したモデルを挙げたいです。
「62GS」(1967年)は、グランドセイコー初の自動巻で、ベゼル(風防の周りの枠)がない「ベゼルレス」デザインが特徴です。
ベゼルがないということは、ケース側面(ラグ)の造形と磨きが、時計の印象を決定づけるということ。この大胆なデザインを支えているのが、間違いなくザラツ研磨ですね。
SBGA211(通称:雪白)

グランドセイコーの中でも絶大な人気を誇る、通称「雪白」モデル。このモデルのすごいところは、ケースとブレスレットの素材に「ブライトチタン」を採用している点です。
前のセクションでも触れましたが、チタンはステンレスの約1.5倍もの研磨時間を要する難素材なんです。軽い反面、ステンレスとは異なる加工の難しさがあるんですね。
にもかかわらず、ザラツ研磨によって、そのケース側面やブレスレットの駒には、チタンとは思えないほどの歪みのない完璧な鏡面仕上げが施されています。
そして、この鋭い鏡面の「輝き」が、文字盤の「雪白」パターンのような繊細でマットな質感と、見事なコントラストを生み出しているんです。
光と影、強さと繊細さ。その対比を腕元で楽しめる、ザラツ研磨の価値が凝縮された一本かなと思います。
62GS 現代デザインモデル


グランドセイコーの歴史を語る上で欠かせない「62GS」(1967年)のデザインを現代に受け継ぐモデル群ですね。このデザインの最大の特徴は、風防の周りの枠である「ベゼル」がない、ベゼルレス構造にあります。
ベゼルがないということは、時計の「顔」の印象が、文字盤と、あとはもうケース側面(ラグ)の造形と「磨き」だけで決まってしまう、ということなんです。これって、すごく大胆なデザインですよね。
もしここでケース側面の研磨が凡庸で、エッジが丸まっていたら、全体が間延びした印象になってしまうはずです。
62GSの現代デザインモデルは、ザラツ研磨によって磨き上げられた多面的なケース造形と、鋭く切り立った稜線があるからこそ、この開放感ある意匠に「緊張感」と「高級感」を与え、デザイン全体の審美的な「背骨」として機能しているんです。
 管理人
管理人まさにザラツ研磨の真価が問われるデザインだと思います。
カシオ MR-Gの代表モデル

MR-Gは、G-SHOCKのアイコニックなデザインを、いかに高級なフルメタルで表現するかにザラツ研磨が活かされています。
特に「フロッグマン」のような左右非対称で複雑な形状のモデルにザラツ研磨を適用しているのは、カシオの技術力の高さを感じますね。
MRG-BF1000R(フロッグマン)

G-SHOCKの中でも、ダイバーズウォッチとして特にアイコニックな「フロッグマン」。その最大の特徴である「左右非対称デザイン」を、フルメタルで、しかもMR-Gのクオリティで実現したモデルです。
このデザインは、センサーや機能を考慮したもので、非常に複雑な形状をしています。MR-Gは耐衝撃性のために多数の金属パーツを組み合わせてケースを構成しているんですが、このモデルも例外ではありません。
その極めて複雑な形状のケース部品、その一つひとつに、職人が手作業でザラツ研磨を適用しているんです。
樹脂なら一体成型できるような形も、金属で、しかもエッジを立てて磨き上げるのは本当に大変なことだと思います。
 管理人
管理人この途方もない手間こそが、G-SHOCKの絶対的なタフネスと、高級時計としての「造形美」を両立させているんですね。
MRG-B2000B(勝色)

こちらは、日本の伝統色である「勝色(かちいろ)」(濃い紺色)をテーマにしたモデルです。MR-Gはこうした日本の伝統的な美意識を取り入れるのが得意ですよね。
このモデルの魅力は、ベースとなるブラック基調のデザイン(多くはDLCなどの硬質なコーティングが施されています)の中に、アクセントとしてザラツ研磨による鏡面が配置されている点です。
複雑な面構成を持つ金属パーツの「エッジ部分」や「特定の面」に、ザラツ研磨による歪みのない鏡面が光る。
そうすることで、オールブラックの中でも時計全体が重たい印象にならず、立体感とシャープさが際立つんです。
まるで、日本の鎧や刀が持つ、機能的ながらも美しい「輝き」のアクセント。
 管理人
管理人ザラツ研磨が「下地処理」として、そして「美のアクセント」として見事に機能している好例かなと思います。
ザラツ研磨は様々なブランドで採用されている
ザラツ研磨は、グランドセイコーやカシオだけの独占技術というわけではありません。日本の「ものづくり」の精神を受け継ぐ、他の複数の高級時計ブランドでも、この高度な研磨技術は採用されています。
それぞれのブランドが、ザラツ研磨に対して独自のアプローチや哲学を持っており、その活かし方に個性が表れている点が非常に興味深いです。
MINASE(ミナセ) / DIVIDO (VM14)
MINASEは、時計コレクターの間で「Sallaz(ザラツ)研磨と言えばMINASE」と呼ばれるほど、この技術をブランドの象徴として位置づけています。
DIVIDO (VM14)などのモデルでは、そのこだわりが強く表れています。彼らの最大の特徴は、研磨をケースの一部分に限定しない点にあります。
ケース本体の複雑な構造部分はもちろん、文字盤のインデックスやブレスレットの駒(こま)一つひとつに至るまで、通常は磨かれないような細かな断面のすべてに、徹底的にザラツ研磨を施しているのです。
これは、大量生産とは逆行する、情熱と膨大な作業時間を注ぎ込むMINASEの哲学そのものを示していると言えるでしょう。
カシオ(CASIO) / MR-G (MRG-B2000D)
カシオは、G-SHOCKの最高峰ラインである「MR-G」においてザラツ研磨を採用しています。一般的に、ザラツ研磨は平面を磨くことを得意とするため、デザインにある程度の制約が生まれがちです。
しかしカシオのアプローチは独特で、MR-G (MRG-B2000D)のような非常に複雑な形状を持つデザインを優先し、そこにザラツ研磨の技術を合わせ込むという難易度の高い手法を選択しました。
タフネスと美しさを両立させるため、シャープな造形を際立たせる研磨が不可欠なのです。
シチズン(CITIZEN) / The CITIZEN (NC1001-58A)
シチズンの最高級ラインである「ザ・シチズン」でも、ザラツ研磨が採用されています。
NC1001-58Aなどのモデルに見られるように、ザ・シチズンのデザインは、奇をてらわず平面を多用したオーセンティック(正統派)なスタイルが特徴となっています。
このデザインは、ザラツ研磨の長所を最大限に活かす上で非常に合理的です。歪みのない平滑な面を磨き上げることで生まれる、透明感のある輝きとシャープなエッジが、時計の品格を一層高めているのです。
Knot(ノット) / AT-38
Knotは、高品質な時計を適正な価格で提供することを目指しているですJAPANブランド。フラッグシップモデルの「AT-38」では、ケース製造に「林精器製造株式会社」を起用しています。
林精器製造株式会社は、グランドセイコーのケース製造も手掛ける、世界最高水準の金属精密加工技術を持つメーカーとして知られています。
AT-38のケースにも、熟練職人による高度なザラツ研磨技術が施されています。これにより、多くの人が手に取りやすい価格帯でありながら、高級時計に匹敵するシャープな輝きを実現している点が大きな魅力です。
オリエント(ORIENT) / ロイヤルオリエント (WE0011JD)
現在は販売が終了していますが、かつてのオリエントの最上位ライン「ロイヤルオリエント」でもザラツ研磨が採用されていました。WE0011JDといったモデルは、その仕上げの美しさで知られています。
シンプルでスタンダードなデザインの中に、ザラツ研磨によって歪みなく磨かれたケースが強い輝きを放ちます。時計愛好家の間では、その輝きはグランドセイコーと比べても遜色のないレベルにあると高く評価されていました。
ザラツ研磨の価値と所有する意味

ここまで見てきたように、ザラツ研磨は単なるピカピカにする技術ではありませんでしたね。
スイスの「Sallaz社」の機械を源流に持ちながらも、日本の職人たちの「経験と感覚」によって独自の進化を遂げた、日本の高級時計製造における「クラフツマンシップの象徴」。それがザラツ研磨なのかなと、私は思います。
私たちがその「歪みのない鏡面」に惹かれるのは、そこに(プラチナならステンレスの5倍以上にもなる)圧倒的な手仕事の時間と、作り手の執念、そして美意識が凝縮されているのを感じるからかもしれません。
ザラツ研磨が施された時計を所有するということは、光を歪みなく反射する完璧な平面と、鋭く切り立った稜線という、機械の自動化では到達できない「工芸品」を手首に纏うことなんだと思います。
そう考えると、自分の時計がさらに愛おしくなってきませんか?